ARTICLES
ARTIST
#奥田栄希
2025.02.28
奥田栄希 DIG SHIBUYA記念インタビュー Part2 “ゲーム”と“アート”の境界線はどこにあるか
Interviewer: 坂本遼󠄁佑
2025年2月8日から2月11日までの4日間で開催されたアート×テックの祭典「DIG SHIBUYA」。その企画のひとつとして“みんなでやるRPG”をコンセプトに、ゲーム作品『パソコンクエスト』のイベントを開催したピクセルクリエイターの奥田栄希氏に特別インタビュー! YouTubeのライブ配信を通して複数のユーザーが同時にプレイできる、新感覚ゲーム誕生までの舞台裏を深掘りした。(文=坂本遼󠄁佑|Ryosuke Sakamoto)
ロボットのコスプレも“パブリックアート”の一部
| 坂本 | 今年のDIG SHIBUYAの開催に合わせて、新たに開発されたゲーム作品『パソコンクエスト』ですが、一番苦労された点はどこだったんですか? |
|---|---|
| 奥田栄希 | イベント当日のロボットのコスプレですかね、、、。 |
| 坂本 | ゲームソフトの開発ではなく!?(笑) |
| 奥田栄希 | 街中での展示なので少しでも多く人の目を引きたくて。高校の学園祭みたいに目立つ着ぐるみがいたら、親子連れやカップルが反応してくれるかなと思ったんです。ロボットのコスチュームを着ることなんて、人生でほぼないのでいい思い出にもなるし(笑) |
![]() 会場に訪れた子供たちと楽しそうに触れ合う奥田氏
会場に訪れた子供たちと楽しそうに触れ合う奥田氏
| 坂本 | アーティストとしてだけでなく、企画者としてもイベントのことを考えないといけないですもんね。今回のようなパブリックな場で作品を展示したのは、奥田さんにとって初めてのことだったんですか? |
|---|---|
| 奥田栄希 | 以前、西荻窪の商店街などで展示をしたことはあったのですが、こんな巨大ビジョンに作品を映し出したのは、今までにない初めての試みでした。 |
| 坂本 | ギャラリーなどの展示とは異なり、すべての人がアートに興味があるというわけでない。まさに、新たな“挑戦”だったんですね。 |
| 奥田栄希 | もともとDIG SHIBUYAには、アート系のイベントではあるのですが、どこか“お祭り”のような雰囲気があり、すべての人が気軽にアートに触れ合えるのが最大の魅力。なので、パソコンクエストも親しみやすい印象にしたかったんです。 |
![]() パソコンクエストのQRコードを見せながら観客を楽しませる
パソコンクエストのQRコードを見せながら観客を楽しませる
| ぼくは、アートをより敷居の低いものにしたくて、あえてゲームを“アート作品”として制作しているところがあって。客寄せなどに使われる着ぐるみも、ある意味“庶民的なもの”の象徴じゃないですか。今回の企画にぴったりだと思いました。 | |
| 坂本 | ロボットのコスプレもいい味を出してますね(笑) |
| 奥田栄希 | でも、思ったより視界が狭くて歩きづらく、ピンマイクなども付いていないので、人前で話しても声がちゃんと届かなくて。一方、道ゆく人たちに手を振ったら、みんな振り返してくれて、通常の展示会にはない嬉しさがありました(笑) |
“ゲーム”と“アート”の境界線はどこにあるか
| 坂本 | 奥田さんのゲーム作品は、実際にプレイできるものが多く、どこか身近な存在に感じます。 |
|---|---|
| 奥田栄希 | それもアートの敷居を低くするための、自分なりのこだわりだったりします。ただ鑑賞するだけでなく、多くの人に作品を体感して欲しくて。 |
| 坂本 | 体感できるアートということですね。奥田さんにとって“ゲーム”と“アート”の境界線はどこにあるんですか? |
| 奥田栄希 | 本来、ゲームは商業的な目的で開発されたものなので、企業にとっては“お金を稼ぐこと”が最大の目的だった。なので、いかに“売れる”ゲームソフトを開発して、どうやってマネタイズするかが重要視されていたんです。 |
| 一方で、アートは“売ること”だけが目的ではない。むしろ、商業的ではないものにこそ、アートとしての価値が生まれることもあって。それと同じ現象をゲームでも起こすことができないかと考えたんです。 | |
| 坂本 | あえて“売れないゲーム”を作るということですか? |
| 奥田栄希 | そうです。例えば、かつて“世界にひとつしかないクソゲー”をコンセプトに、遊び要素をすべて排除した不毛なゲーム『悲しいゲーム』という、シリーズものの作品を制作したことがありました。 |
![]() 悲しいゲームシーリーズ『SHOOTING GAME』(2015)
悲しいゲームシーリーズ『SHOOTING GAME』(2015)
| そのなかのひとつ『DEAD GAME』(2015)という作品では、空中に浮かぶ「LIVE」と書かれたブロックにキャラクターが立っていて、左右に移動やジャンプをしても画面下に落ちてもとの状態に戻るだけ。いくらやってもゴールがなく、ただ虚無感を覚えるだけなんです。 | |
| 坂本 | 確かにつまらなそう、、、(笑) |
| 奥田栄希 | ゲームなのにスタートもゴールもない。これではどうやっても売れないですよね。だからこそ、真の“アート作品”だと言えると思うんです。 |
| 坂本 | つまり、“完璧なゲーム”を目指すのとは違うんですね。 |
| 奥田栄希 | そうなんです。だから、今回のDIG SHIBUYAに出展した『パソコンクエスト』も、最初に“みんなでやるRPG”というコンセプトにあったので、一応、スタートとゴールは設定したものの、ゲームとしては“良作”とは言えません。 |
| だって、シングルプレイで遊べるゲームの方が、RPGとしては絶対に楽ですよね。複数のプレイヤーが同時に操作をしたら、ゲームが“自分のもの”ではなくなってしまう。でも、それがアート作品としては大切な要素だったりします。 | |
| 坂本 | まさに“不便益”がゲームをアートにしているんですね。 |
![]() 悲しいゲームシーリーズ『DEAD GAME』(2014)
悲しいゲームシーリーズ『DEAD GAME』(2014)
奥田栄希が持つ渋谷のイメージとは
| 坂本 | 奥田さんは東京出身とのことですが、どの辺のエリアで生まれ育ったんですか? |
|---|---|
| 奥田栄希 | 豊島園のあたりです。 |
| 坂本 | 豊島園の近くだったんですね! ぼくも練馬区出身なので、よく豊島園には遊びに行っていました。 |
| 奥田栄希 | 今はもう豊島園はなくなってしまいましたが、中学校の卒業遠足も豊島園に行ったくらいなので、たくさんの思い出が詰まっていますね。 |
| 坂本 | 地元の人はみんな行っていたと思います。 |
| 奥田栄希 | 父親が子供の頃からあった遊園地なので、閉園した時は父親の方が寂しかったんじゃないかな。 |
| 坂本 | あれは本当にショックな出来事でした。では、渋谷にもよく遊びに出かけられていたんですか? |
| 奥田栄希 | 近くだったんですがあまり遊びに来ることはなくて。シブヤピクセルアートの企画に参加するようになってから、代表の坂口さんに呼ばれて行くことが多くなりました。 |
![]()
| 坂本 | では、遊びに行く場所ではなかったんですね。よく渋谷を訪れるようになってからは、街のイメージなどは変わりましたか? |
|---|---|
| 奥田栄希 | 最近だと、駅前にShibuya Sakura Stageが建設されて、急激に変化している街という印象を持ちました。文化が息づいていて、いろんな人が行き交っているけど、ちょっとエッチなスポットもある(笑)面白い街だなと思います。 |
| 坂本 | 渋谷ならではの空気感がありますよね(笑) |
| 奥田栄希 | 今では海外からの観光客も増えてきているし、これからまた変わっていく街でもあります。 |
| 坂本 | 奥田さんが持つ渋谷のイメージもさらに更新されていきそうですね。 |
- 奥田栄希
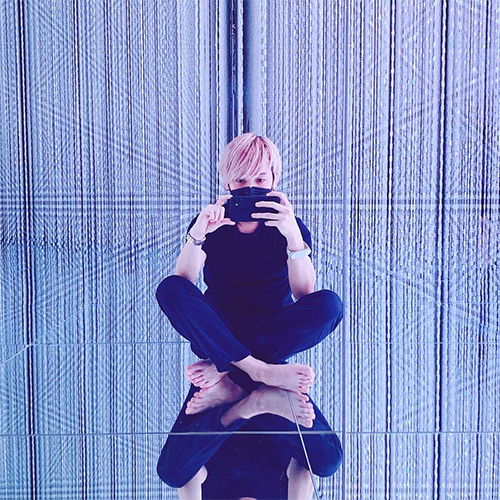
- Interviewer: 坂本遼󠄁佑 the PIXEL magazine 編集長。東京都練馬区出身。大学ではアメリカの宗教哲学を専攻。卒業後は、出版社・幻冬舎に入社し、男性向け雑誌『GOETHE』の編集や、書籍の編集やプロモーションに携わる。2023年にフリーランスとして独立し、現在はエディター兼ライターとして活動している。